レーザー光の原理
レーザーとは
光とは
光とは「電磁波」の一種です。「電磁波」には波長という基準があり、波長の長い方から、 電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・ガンマ線などと呼び分けられます。
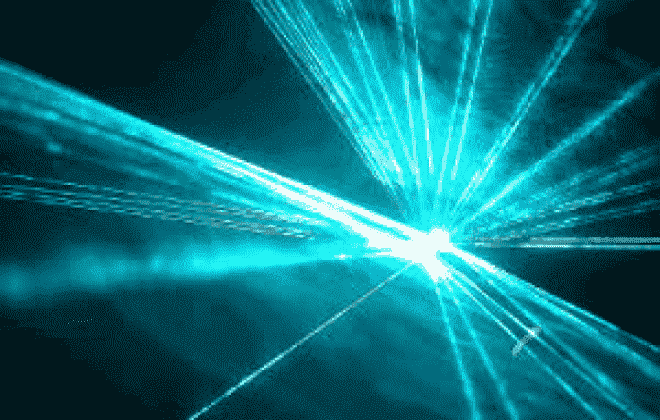
レーザー光の特徴
直進性
レーザー光はまっすぐに進みます。 精密な機械や熟練した職人が本気で作る定規よりも精密で真直ぐです。 レーザー光は位置を割り出すための測量計に使われており、 高層建造物や高速道路といった1ミリのずれも許されない工事などの計測機器に使われてします。
高エネルギー密度
レーザー光のエネルギー密度は非常に高く、普通の光と同じようにレンズで集光することができます。
集光したレーザー光を利用して金属を切断したり、溶接といった加工の分野にも使用されています。
さらには、ダイヤモンドの加工から医療用のメスとして、幅の広い用途に使用されています。
単色性
レーザー光は単色です。
普通の光には沢山の色(波長)の光が含まれていますがレーザー光は色(波長)の揃った光です。
この光を利用してCDやDVDメディアの読み書きに利用されています。
CDの表面には凹凸があり、このビット情報をレーザーで検出して音や映像に変えています。
また書き込みの時はCDの表面をレーザー光で熱して凸凹を作ります。
波長を短くすることで小さな凸凹を読み取ったり、作ったりすることができます。
昨今、レーザーの性能も上がり、より波長が短い青紫色のレーザーが開発され、より小さな高密度で凸凹を作るブルーレイディスクが誕生しました。
可干渉性(コヒーレンス)
レーザーはコヒーレンスです。
コヒーレンスとは可干渉性という意味です。
レーザー光の最も大きな特徴はコヒーレンス(可干渉性)です。
一般の光は自然放出光であるため,光波の位相,エネルギーはランダムであり,干渉することはありません。
しかし,レーザー光は誘導放出により発生する光であるため,光波の位相,エネルギーがそろっており干渉します。
波は条件が整えば重ね合わせることができます。これが干渉です。
レーザー光の発生原理
レーザー光はどうやってできるか
レーザー光の「原料」とはなんでしょうか?また、レーザー光を作り出すためにはどんな「道具」が必要になるのでしょうか? おおまかに並べてみると、次のようになります。
材料 |
ルビー(レーザー媒質(バイシツ))
|
|---|---|
道具 |
共振器(全反射の鏡と半反射の鏡のセット) |
基本的にはこれでレーザー光が作り出せます。レーザー装置には他にもいろいろな部品が組み込まれています。 それらはみな補助的な働きをしているだけで(冷却やレーザー光の供給経路確保、安全装置等)、「レーザー光を作る」働きをしているわけではありません。
レーザー媒質や励起源
レーザー媒質 |
液体:色素(ダイ)等
|
|---|---|
励起源と対応媒質 |
放電方式:He-Neレーザー、アルゴンレーザー、CO2レーザー、エキシマレーザー等
|
共振器 |
反射鏡2枚(全反射・半反射)でレーザー媒質をはさんだもの。平面型や球面型のものがある。 |
この装置からレーザー光を発振させる仕組みとはどういったものか?
(1)レーザー媒質を全反射鏡と半反射鏡で挟み、励起源からエネルギーを与える
(2)レーザー媒質の電子がエネルギーに反応して励起状態になる
(3)励起状態となって放出された電子が反射鏡の間で共振し、増幅される
(4)増幅されたエネルギーが一定のレベルを超えると、半反射鏡の側から光線となって発振される。このとき、2枚の反射鏡間の距離が、レーザー媒質の持つ波長の整数倍になっていないと、共振・増幅に至らない
レーザー媒質に光や電圧によるエネルギーを与えると、物質の原子構造が影響を受け、不安定な動きをする電子が、 低いエネルギー状態からより高いエネルギー状態に移ります。これを励起と言います。 しかし、励起した電子は、高いエネルギー状態のところに長居することができないので、すぐに元のところに戻ります。 その戻る時に発生するエネルギーが、レーザー光となります。 このエネルギーは何度発生させても常に一定です。 こうして発生したレーザー光を全反射鏡と半反射鏡との間で反射させることで、 レーザーのパワーがいくつも重ねられて(共振して)増幅します。 増幅したパワーがある一定のレベルに達すると、半反射鏡を通り越して、外へ出ます。 こうして半反射鏡の外に出てきたレーザーパワーが、最終的にハンドピースの先まで送られます。